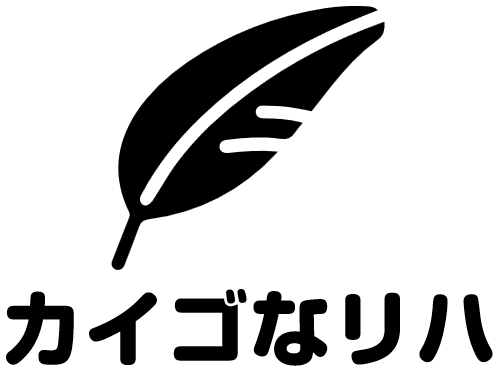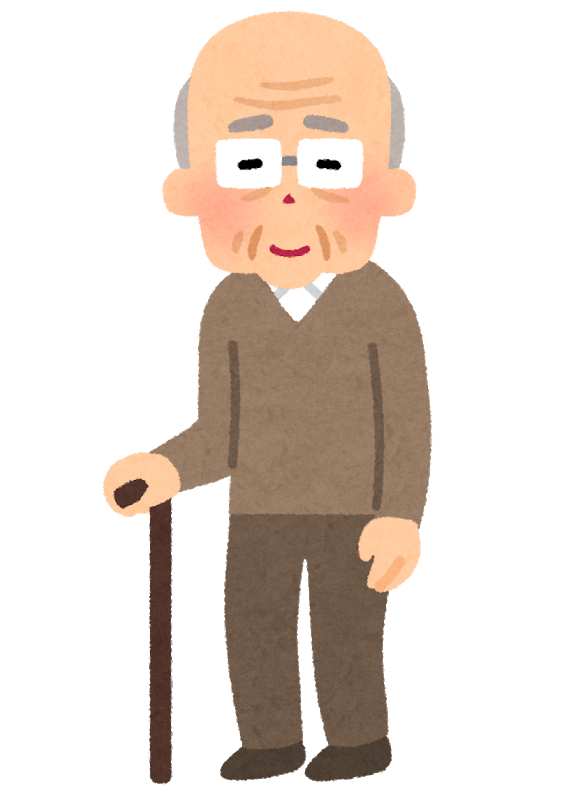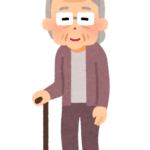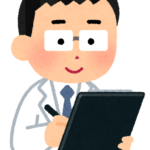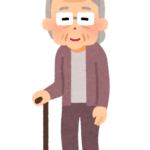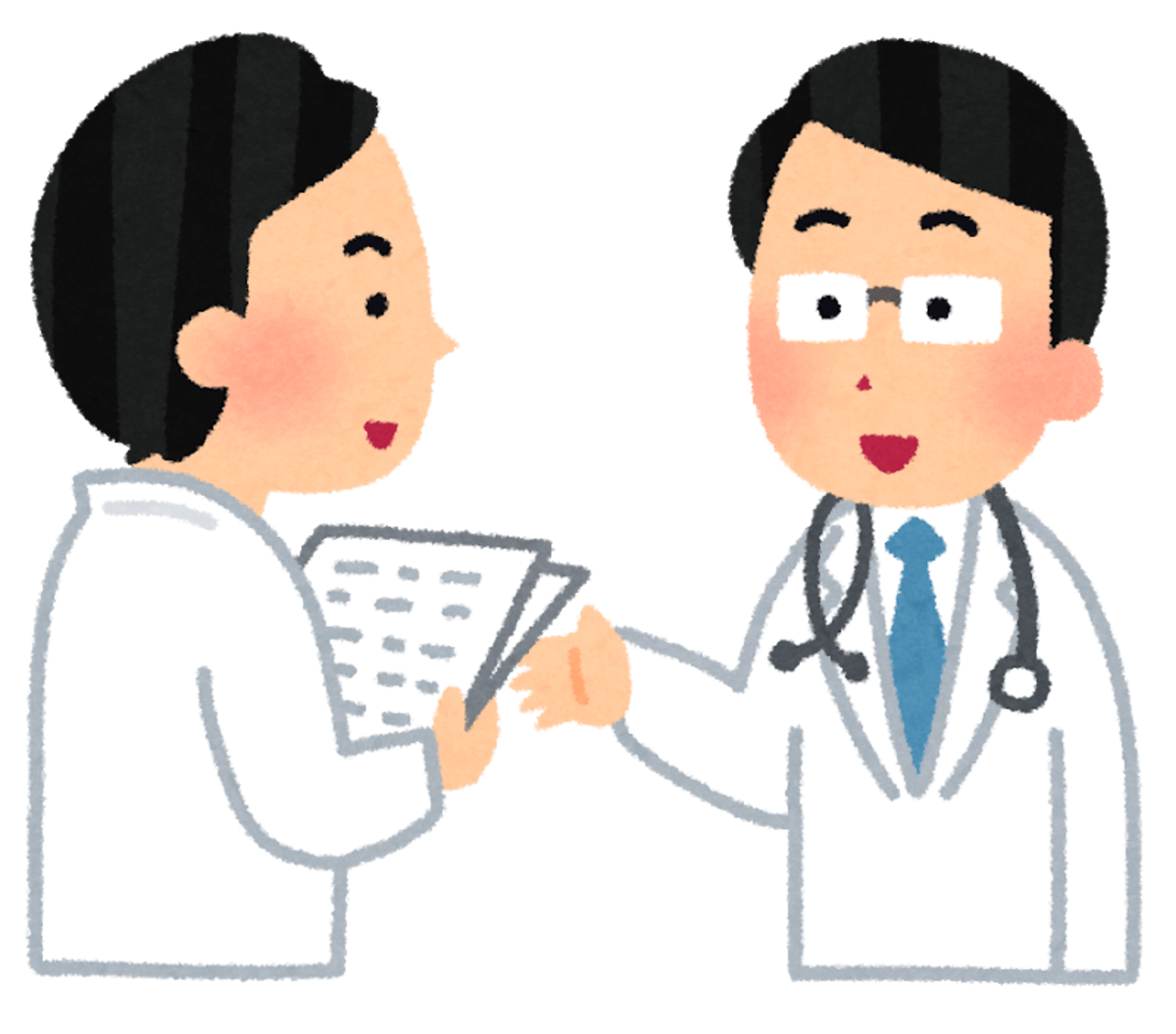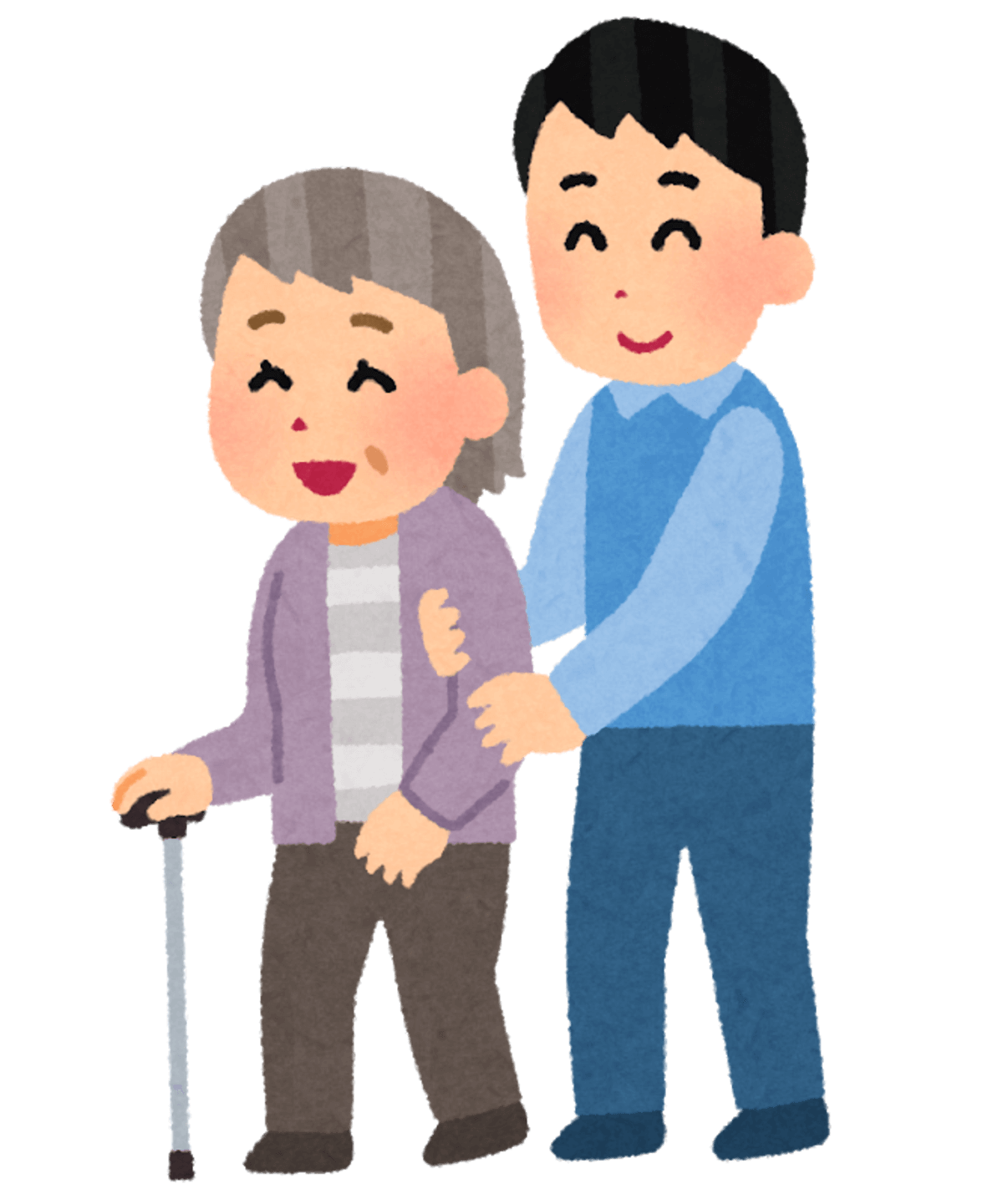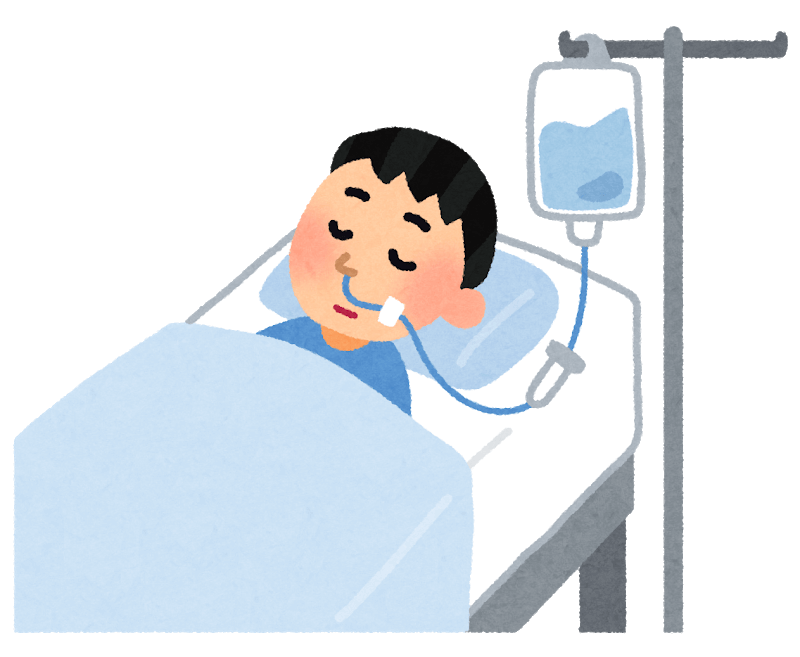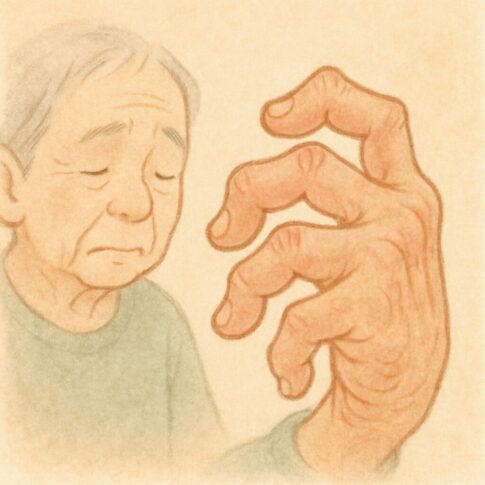いつもお世話になっております!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
在宅サービスの一つである『認知症対応型共同生活介護』。
通称『認知症グループホーム』
認知症グループホームも人生の最期まで住むことが出来る施設です。
この認知症グループホームで算定できる加算『看取り介護加算』があります。
令和3年度では『ガイドライン』や『算定日数の変更』等が変更となりました。
って、ことで今回は『【令和3年度】算定日数が増えた?認知症グループホームでの看取り介護加算の算定要件』について話したいと思います。
▼目次▼
1.看取り介護加算とは?(令和3年度変更点)
認知症グループホームでは利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援する事を目的としてます。
認知症グループホームで看取りの対応を行った場合に算定できる加算が『看取り介護加算』です。
看取り介護加算は医師が医学的知見に基づいて
回復の見込みがないと診断した利用者
に行うこととなっています。
また令和3年度の介護報酬改定では中重度者や看取りへの対応の充実を図る為以下の内容が変更・追加となっています。
- 死亡日以前45日より算定可能
- 『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』に沿った対応
因みに異なる施設サービスの看取り介護加算はコチラ
2.取得可能施設サービス
認知症対応型共同生活介護での看取り介護加算が算定できる施設は以下のようになっています。
- 認知症対応型共同生活介護
3.取得単位数
認知症対応型共同生活介護での看取り介護加算の取得単位数は以下のようになっています。
令和3年度の介護報酬改定で死亡日以前の45日から算定可能となりました。
- 看取り介護加算
| 日数 | 単位数 |
| 死亡日以前31日以上45日以下 | 72単位/日(新設) |
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位/日 |
| 死亡日の前日及び前々日 | 680単位/日 |
| 死亡日 | 1,280単位/日 |
4.算定できない要件
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では算定できない要件もあります。
それは以下の通りとなっています。
退居した日の翌日から死亡日までの間
又は
医療連携体制加算を算定していない
5.算定要件
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算の算定要件は以下のようになっています。
5.1.利用者または家族の同意
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では今後の療養や介護等の看取りに関する指針を定める必要があります。
この看取りに関する指針を定め、入居の際に利用者や家族に指針の内容を説明し、同意を得なければなりません。
また利用者の状態や家族の求めなどに応じて、随時医師等と相互連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む)であることが必要です。
5.2.看取りに関する指針の見直し
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では、認知症対応型共同生活介護の看取りの実績等を踏まえて、適宜看取りに関する指針の見直しを行う必要があります。
協議に出席する職種として以下のようになっています。
- 医師
- 看護職員
- 介護職員
- 介護支援専門員
- その他の職種
なお、認知症対応型共同生活介護の看護職員以外にも以下に所属する看護職員も協議に可能です。
- 密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院
- 診療所
- 訪問看護ステーション
5.3.看取りに関する職員研修
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では職員に向けて看取りに関する職員研修を行うことが必要とされています。
5.4.看取り対象者
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算での対象者として以下に当てはまる方が対象となっています。
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み
がないと診断した者
5.5.介護に係る計画に同意している
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では
- 医師
- 看護職員(密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所、訪問看護ステーション)
- 介護支援専門員
- その他の職種
が共同で利用者の介護に係る計画を作成。
この利用者の介護に係る計画を医師などその内容に応じた職員から説明、同意をしている利用者である必要があります。
6.留意事項
6.1.看護職員について
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算での看護職員は、利用者の状態に応じて随時対応が出来る施設が重要となってきます。
これは認知症対応型共同生活介護と密接な連携を確保できる範囲にある必要があります。
具体的には
同一市町村内に所在している
または
同一市町村内に存在しない場合でも
自動車等の移動で20分以内の近距離
にある必要があります。
6.2.看取り介護の質を向上させるために
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では、看取り介護の質を常に向上させていく為、
- (Plan):看取りに関する指針を定め施設の看取りに対する方針等を明らかにする
- (Do):看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る計画に基づいて、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う
- (Check):多職種が参加するケアカンファレンス等を通じ、実施した看取り介護の検証や、職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う
- (Action):看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを行う
のPDCAサイクルを行うことが重要となっています。
なお、看取り介護の改善の為
適宜、家族等に
- 看取り介護に関する報告会
- 利用者等、地域住民との意見交換(地域への啓発活動)
を行うことが望ましいとなっています。
6.3.質に高い看取り介護の実施の為に
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では、多職種連携し利用者等に対して十分な説明、理解を得るように努めなければなりません。
具体的に以下の内容を利用者に理解が得られるように継続的に説明していきます。
- 終末期にたどる経過
- 看取りに際して行う可能性のある医療行為の選択肢
- 医師や医療機関との連携体制
また説明の際は
利用者に関する記録を活用した説明資料の作成し、その写しを提供します。
6.4.看取りに関する指針
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では看取りに関する指針が定められている必要があります。
看取りに関する指針は管理者を中心として以下の職員が協議し定めます。
- 看護職員
- 介護職員
- 介護支援専門員等
また看取りに関する指針に盛り込むべき項目の例として以下が挙げられます。
- 当該事業所の看取りに関する考え方
- 終末期にたどる経過(時期、プロセスごと)とそれに応じた介護の考え方
- 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
- 医師や医療機関との連携体制(夜間及び緊急時の対応を含む)
- 利用者等への情報提供及び意思確認の方法
- 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
- 家族等への心理的支援に関する考え方
- その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の方法
6.5.重度化した場合の対応に係る指針との兼ね合い(医療連携体制加算)
認知症対応型共同生活介護には医療連携体制加算というのがあります。
この医療連携体制加算の施設基準には以下の説明文があります。
重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
この『重度化した場合の対応に係る指針』に看取りに関する指針に盛り込むべき内容を記載した場合。
この記載で看取りに関する指針の作成に代えることが出来ます。
ただし看取りに関する指針と同様に適宜見直しを行う必要があります。
6.6.看取り介護の記録&情報共有
認知症対応型共同生活介護での看取り介護加算を実施するにあたり、看取り介護の記録や多職種との情報共有に努めていかなければなりません。
以下の事に留意して行っていきましょう。
- 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録
- 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記録
- 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメント及び対応についての記録
また
利用者等に対する随時の説明に係る同意を口頭で得た場合。
介護記録に以下の内容を記載しておくことが必要です。
- 説明日時
- 内容等
- 同意を得た旨
6.7.死亡前に帰宅や医療機関へ入院した場合
認知症対応型共同生活介護での看取り介護加算では死亡日を含めて45日を上限に算定できます。
しかし
死亡前に自宅へ戻るや医療機関へ入院した後に自宅や入院先で死亡した場合。
認知症対応型共同生活介護で
看取り介護を直接行っていない退去した日の翌日
~
死亡日
までは算定できません。
6.8.人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたって以下のガイドラインを参考にします。
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等
を参考にして、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるように多職種連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めることが大切です。
6.9.看取り介護加算は死亡月にまとめて算定
看取り介護加算は死亡月にまとめて算定する形となっています。
なので看取り介護加算は退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能です。
利用者側にとっては、認知症対応型共同生活介護に入居していない月についても自己負担を請求されることになります。
ですので利用者が退居等する際に、退居等の翌月に亡くなった場合、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明することが大事です。
このことを文書で同意を得ておくことが必要であることに注意しましょう。
6.10.退去後も指導や情報提供を行う
認知症対応型共同生活介護の場合。
退去等の後でも継続して
- 利用者の家族指導
- 医療機関に対する情報提供
が必要となっています。
このように連携を図ることで、利用者の死亡を確認することができます。
なお情報の共有を円滑に行う観点から、入院先の医療機関が対象の利用者の状態を伝え、認知症対応型共同生活介護に状態を伝える場合。
この際は必ず退去の時に本人又は家族に対して説明、文書にて同意を取っておく必要があります。
6.11.入院や外泊を除いた期間を算定可
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では利用者が入退院や外泊したのが死亡日以前45日の範囲内の場合。
入院または外泊期間を除いた期間の看取り介護加算の算定は可能です。
6.12.当日の所定単位数の算定に左右される
認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算では
- 入院の当日
- 外泊の当日
- 退去の当日
についての看取り介護加算の算定の有無は、その日に所定単位数を算定するかによって決まります。
6.13.月に2人以上の看取り介護加算の常態化
認知症対応型共同生活介護の性質として
- 家庭的な環境
- 地域住民との交流
があり、自立した日常生活を営むことが出来るようにする目的があります。
その為、1月に2人以上が看取り介護加算を算定することが常態化するのは望ましくないとされています。
7.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
8.最後に
認知症対応型共同生活介護は地域住民との交流を持ち、家庭的な環境で利用者の自立した日常生活を営む在宅サービスです。
看取り介護加算を算定するにあたり、医療的措置が必要になったりする場合がありますが、今後も重要となってくる加算です。
算定要件を満たして取得できるようにしていきましょう。